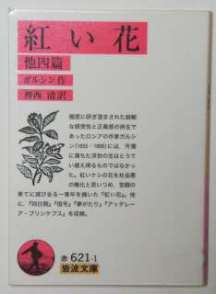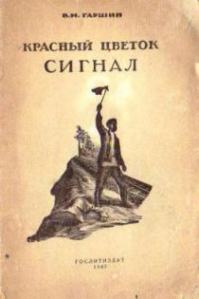ガルシンの短編集「赤い花」(岩波文庫)に収録されている「信号」という作品を、何十年かぶりに読み返してみました。この作品を最初に読んだのは中学3年の時で、当時使用されていた三省堂国語教科書に載っていました。私はこの作品から非常に大きな影響を受け、その後、人生の岐路に立たされたとき、いつもこの作品が頭をよぎります。今回はこの作品について感想を書いてみます。
教科書に載っていたのでストーリーはご存じと思いますが、一応簡単にあらすじを書きます。
時は、帝政ロシアで暗黒の支配が続いていた時代です。主人公のセミョーンは、戦争帰りで、病身な、生活に疲れ切った男でした。ようやく鉄道線路番の仕事にありつき、女房と二人、線路の番小屋で畑を耕しながら慎ましやかな生活を始めます。長い放浪生活の後に、やっと小さな幸せを見つけたのです。
もう一人の主人公ヴァシーリイは、隣の番小屋の陰気な男。二人は知り合い、土手の上で生き方を語り合うようになります。ヴァシーリイは現在の生活には満足せず、社会に対する不平や不満を述べ立てます。そして、彼は上司の不当性を訴えるためモスクワへ直訴に及びます。しかし、直訴は失敗に終わり、捨て鉢となったヴァシーリイは、線路のレールをはずし列車の転覆を企るのです。
これを発見したセミョーンは、やめさせようとしますがすでに遅く、遠くから列車の近づく気配を聞きます。セミョーンは自らの体を突き刺し、流れる血でハンカチを染め赤旗を作り、列車を止めようと必死に振るのです。・・・・・・。
というような物語です。セミョーンの生き方に一面的にとらわれ過ぎると、道徳臭い作品のように思われるかもしれません。事実、この作品は、正義や自己犠牲を教える道徳の副教材としても利用されているようです。しかし、それは少し違うと思います。
著者のガルシンは、セミョーンをささやかな幸せを求めつつも、崇高な正義感と美しい自己犠牲に生きた信仰深い人物として描きました。一方、ヴァシーリイは、帝政ロシアの支配に不平不満を述べ立て反抗する陰鬱な人物として描かれました。ガルシンが生きた時代は、ナロードニキ運動がしだいに広がりをみせていった時代でした。帝政ロシアという抑圧の時代を必死に生きた民衆。ガルシンは、その民衆の中の典型的な二人の人物を描き出したのです。ヴァシーリイの描かれ方は、個人的なレベルの抵抗としてしか描かれていないという限界はありますが・・。
中学生だった私は、この作品は「あなたは、セミョーンの如く生きるのか? それともヴァシーリイの如く生きるのか?」を問うている作品だと思いました。その時以来ずっと、私の心の中にはセミョーンとヴァシーリイの二人が、苦悩の表情を浮かべ、議論を繰り返しながら住み続けています。いかに生きるべきか岐路に立ったとき、必ず二人が現れて議論を始めるのです。
私は、今までどのように生てきたのでしょうか。セミョーンのような崇高な自己犠牲の人生は送ることは出来ませんでした。ヴァシーリイのような抵抗の人生に徹することも出来ませんでした。しかし、私は今も二人のことを忘れたことはありません。
原発事故。集団的自衛権行使。高まるナショナリズム。非正規労働は全労働者の4割に迫り、ワーキンングプアという言葉で語られ、秘密保護法が施行されようとしている、閉塞感に満ちた現在の社会。私には、「ヴァシーリイを忘れるな!」という叫び声が聞こえるような気がします。
33歳の若さで自殺したガルシンがどのような意図を持ってこの作品を書いたのか、文学的な素養のない私には分かりません。しかし、大きな影響を受けたことは確かです。