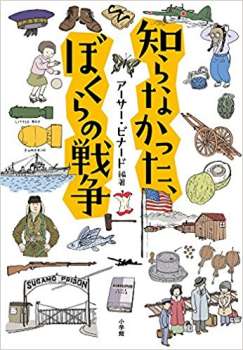アーサー・ビナード著、「知らなかった、ぼくらの戦争」(小学館)を読みましたので、拙い感想を書かせていただきます。
著者のアーサー・ビナード氏は、アメリカ出身の詩人です。日本語で詩を書き、中原中也賞を受賞されています。私は以前に、アーサー・ビナード著「もしも、詩があったら」(光文社新書)の感想を書きました。もしよければ → こちら
「知らなかった、ぼくらの戦争」は、日本民間放送連盟賞・2016年番組部門[ラジオ報道番組]最優秀賞を受賞した、文化放送「アーサー・ビナード『探しています』」という番組で、著者がインタビューした戦争体験者23人の証言をもとに作られた本です。
著者は、持ち前の機知に富んだ軽妙な語り口で、日米の戦争への意識の違いなどを考察し、戦争の本質に迫っていきます。一味違った、戦争体験証言集になっています。
一部分の紹介になりますが、スペースの許す限り紹介してみます。
*****
アメリカの大学を卒業して来日した著者が驚いたのは、日本には「戦後○○年」という表現が当たり前に根付いていることです。朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争……。アメリカでは「戦後」というと、どの戦争のことを指すのかはっきりしないのです。「戦後」のない国に育ったことに気付いた著者。「戦争とはいったい何なのか?」という問題の核心に迫っていきます。
最初に登場する証言者は、著者の妻の母親、栗原澪子さんです。
栗原さんが国民学校(小学校)4年生の時、日本軍は「仏印進駐」に成功しました。この時、各学校に記念の「ゴムマリ」が送られ、みんなでバンザイ!をして喜んだそうです。しかし、彼女の母親(つまり著者の義理の祖母)は、日本の勝利には懐疑的だったそうです。愛国少女として育った彼女は、ムキになって食ってかかります。「お母さんのような非国民がいるから日本は勝てないんだ!」と…。
著者は言います。「国家の教育の影響力が、家庭のそれよりも大きいことにも、ぞっとしながらもうなずかされる。」と。
戦争遂行のためには、教育の力を動員する必要があるということなのです。
次の証言者は、真珠湾攻撃に参加したゼロ戦のパイロット原田氏です。
原田氏は、真珠湾攻撃当日、真珠湾には空母は一隻もいなくて、アメリカ軍は事前に攻撃を察知していたに違いないと直感したそうです。
アメリカで育った著者は、日本軍の真珠湾攻撃の卑怯な奇襲作戦を、繰り返し教え込まれました。しかし、本当は、事前に察知していたのではないか、「対日対独宣戦布告」の格好の口実だったのではないか、との仮説を抱きます。アメリカ世論は、この攻撃を機に、堰を切ったように戦争賛成へと変わっていったといいます。
戦争につきものなのが、陰謀とプロパガンダなのですね。
原田氏は、ミッドウェーで負傷します。軍医は、重傷者をほっておいて、比較的軽傷だった原田氏を先に診察します。原田氏の「私じゃなくて、もっと苦しんでいる人の方を早く診てやってくれ」という懇願に、軍医は答えます。「重症を負ってもう使えなくなった者は、いちばん後まわしだ。これが戦争の最前線の決まり」と…。
なんとも、戦争の本質を突いた証言です。特攻攻撃に参加したのは、即席に訓練された、コストの安い若い兵隊が大部分だったという話も頷けますね。
アメリカ移民として、アメリカで戦争を体験した兵坂米子さんの証言では…。
彼女の家族は、収容所に送られ苦しい生活を強いられます。収容所を出てから、ミシガンの田舎に仕事を見つけ家族で住むことになります。戦争が終わり中学へと進学しますが、きっとジャパニーズとして酷い差別を受けるだろうと予想します。しかし、予想に反して、「おまえはジャパニーズじゃないよ」と言われます。アメリカの田舎では、本物のジャパニーズを見たこともなく、「肌が真っ黄色で、目がつり上がって、出っ歯…」というイメージを刷り込まれていたのです。だからジャパニーズじゃないと…。
日本では、「鬼畜米英」とされていました。アメリカではJapでした。戦争とは、民族的な憎しみのプロパガンダを伴うものなのです。
「日系人とまわりの白人と黒人とヒスパニックとチャイニーズが連帯して、地域が破壊されることに抵抗していたなら政府の計画は破綻していたかも…」と、著者は突拍子もないことを夢想します。
BC級戦犯で有罪判決を受け、スガモプリズンに投獄されていた飯田進氏の証言は、戦争責任についての深い意味を考えさせてくれます。
警察予備隊が創設された頃の話し。彼は、自ら獄中にあっても主張します。「戦犯の釈放運動が、日本の再軍備と結びつけられるなら、反対である…」と。日本を愛することと戦争責任の「狭間」で生きた重い証言です。
玉砕した硫黄島で生き残った秋草鶴次氏は、硫黄島は墓場であると、凄まじい体験を証言します。硫黄島は、「玉砕の地」と礼賛されるような場所ではないと…。
著者は「玉砕」とは、「生き残ってはいけない、死んでこそ美しい」、「生き残った人の命が否定されている」言葉であると、「玉砕」の怖ろしい意味を考察しています。
英語では、The Breaking Jewel(砕かれた宝石)と翻訳しているが、これは正しい訳ではないと…。玉が砕けるのではなく、砕けて初めて玉になれるのです。死んでこそ初めて意味があるのです。生き残った者の命は否定されているのです。
こんな調子で紹介していくと、スペースが足りませんね。
この他に、登場する語り手は、次の方々です。
アメリカで強制収容所を経験されたリッチ日高氏。
択捉島の鯨場出身の女性、鳴海冨美子さん。
学徒動員として大久野島で毒ガス工場で働いた元女子学生、岡田黎子さん。
ニューギニアで生き残り、戦後も遺骨収集を続ける西村幸吉氏。
戦艦「大和」の沈没を目撃した駆逐艦「雪風」の乗組員、西崎信夫氏。
満州から修羅場をくぐり奇跡的に生還した漫画家のちばてつや氏。
沖縄、台湾、日本を体験した、与那国島出身の宮良作氏。
疎開船対馬丸撃沈を体験した、平良啓子さん。
沖縄戦を生き延びた沖縄県知事、大田昌秀氏。
喜界島出身の英語詩人、郡山直氏。
落語家の三遊亭金馬師匠。
広島で被爆した、東京都被団協会長の大岩孝平氏。
長崎で「だご汁」を作っていた時に被爆した松原淳氏。
アメリカが原爆投下訓練のため巨大爆弾「パンプキン」を投下していたことを明らかにした金子力氏。
中島飛行機に勤務中、パンプキン爆弾を体験した古内竹二郎氏。
戦後GHQで働いた元事務員、篠原栄子さん。
「日比谷松本楼」のオーナー、権力の中心地近くで戦中戦後を生きた小坂哲郎氏。
アニメ界の巨匠、高畑勲氏。
「戦後のない国」からやって来たビナード氏。「戦争を背負って後始末しながら日々、平和を生み出している人がいる。その営みがあって戦後という日本語は、現在も意味をなしているのじゃないか。」と締めくくっています。
これからも「戦後」をつなぎ続けてゆくための知恵に溢れた本です。お薦めします。
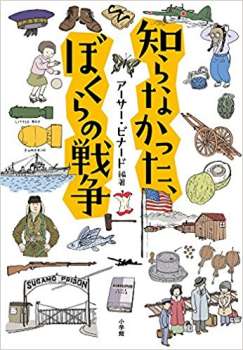
|